◆先日、テレビ関係の人から中国がらみの面白い企画ありませんか、という相談があったのだが、その時の相手のセリフは「ネガティブな話題だけでなく、なんかイイハナシヤナ~、みたいなのも取り上げたいですね」とのことだった。そこで、その時、この本「恵恵」を読んだばかりだったので、「中国でも、こういう、ものすごく、深くていいヒューマンドラマがありますよ」と例に挙げたのだった。
◆中国が憧れた≪純愛≫
◆日本に留学中の中国人女性・恵恵が日本人の高校生教師・健太と恋におち、結婚を約束した矢先に末期の乳癌が発覚。それにもかまわず二人は結婚。健太は言葉も通じない異国の北京で、献身的な看護で恵恵を支え、二人でがんに立ち向かう。彼女は逝ってしまったけれど、その短くも宝石のような愛と闘病の日々を、当事者の健太と、それを見守る母親・付楠が手記につづった。ちょっと「余命1カ月の花嫁」を思い出させるノンフィクション作品である。これはもう、泣くよ、ぜったい。(まあ、私は比較的簡単に泣いちゃうちょろい読者ですが)
◆「恵恵」についてはNHKが報道番組で、特集していたので、今さら同業他社的に大きく取り上げることは難しいだろうが、中国にも、こういうドキュメンタリー映画にしたいような感動的な人間ドラマがいっぱいあるんですよ、と言いかけて、はたと口をつぐんでしまった。本当に、中国で、そんな紅涙を絞るような人間ドラマって他にたくさんあったっけ。じつはそう多くはないのだ。
◆日本では、こういう物語、余命いくばくもないとわかっていても、愛を貫く物語というのは意外にある、と思う。夫の献身の物語も珍しくはない。さっきも触れたが、「余命一か月の花嫁」もそうだ。実は、私自身の周囲にも、恋人(彼女)が末期がんと分かったとたんに、長い同棲生活を解消して結婚したり、離婚する予定だったのに、夫が末期がんだとわかった瞬間、離婚を取りやめて夫の介護を決めた知人・友人がいる。そう、日本では意外にあるのだ、そういう話が身近にも。死が二人を分かつとわかった瞬間、お互いがかけがえのない存在だと確信するドラマ。病魔との戦いで確かめられ深まる愛の物語。わりと身近にある話だから、病気になってしまう側にも、それを支える献身にもがっつり感情移入する。
◆だが、中国はちょっと違うと思う。この本の中国語版原作は、恵恵の母親・付楠さんが書いた「我在天国祝福你」(天国より愛をこめて)という手記。二人の物語はこの手記が刊行される前からテレビ番組や新聞で紹介され、話題となり、ノンフィクションとしては珍しく大ベストセラーとなった。すでに映画化やドラマ化の話も進行中という。なぜ、そこまで報道でも取り上げられるほど話題になったかというと、病という試練にさらされてなお輝く「純愛」の物語というのが、中国でとりわけ、新鮮というか、希少というか、尊いからだったのではないか、と思う。
◆そう感じたのは、この原作に対する読者の主な反応が「うらやましい!」「私も健太みたいな夫が欲しい!」「恵恵はぜんぜんかわいそうではない、だってこんなに深く愛してくれる夫がいるなんて!」という、女性たちの羨望の声だったからだ。この出版当時の読者の反応を私に教えてくれたのは、「恵恵」の翻訳を担当した友人の翻訳家・泉京鹿である。「こういう本を読んで、『うらやましい』って声が出てくるのは中国だよね」と彼女に言われて、確かに、うらやましい、はないよな、と思った。28歳で結婚を控えて末期の乳癌が発覚なんて、悲劇中の悲劇じゃないか?なぜ、うらやましい、という言葉が出てくる?
◆しかし、思わずそういう声が漏れてしまうほど、中国の女性たちにとって「打算のない愛」というものは希少であるということではないかと思う。逆にいえば、中国ではこの程度の悲劇は悲劇に入らないくらいの悲劇がざらにある。
◆こういった中国の社会背景を頭に入れておくと、この本の読みどころも変わってくる。
◆「恵恵」は母親の付楠の手記「我在天国祝福你」と夫・健太の書下ろしの日本語の手記、本来は別々の二つの作品を一つの作品に編んだものである。なので中国で出版される母親視点だけの「我在天国祝福你」と比べると、若干印象が違う。有体にいえば、付楠の視点の方が、恵恵も健太も美化されているのだ。「美化」という言い方はふさわしくないか。つまり付楠さんの目には、健太の行動は、奇跡のように信じられないほどの素晴らしい献身に映っている。その献身を受ける娘も、それだけの価値のあるパーフェクトな女性として描かれている。
◆健太視点でみれば、愛した女性の余命が限られている中で、一分一秒惜しんでそばにいたい気持ちや、彼女が喜ぶことならなんでもしてあげたい気持ちというのは、至極当然のものとして書かれているし、恵恵も完璧な女性ではなく、わがままを言ったり、癇癪を起したり、頑固なところもある普通の女の子として描かれている。日本人の目から見れば、普通のどこにでもいる青年と娘の普通の恋愛。それがこんな風に試練に立ち向かっているから、感情移入してしまうのだ。
◆中国語原作と違って、健太視点の書下ろし部分が入った日本語版「恵恵」は、だから単なる「泣ける純愛闘病ドラマ」というだけではなく、日中の文化や価値観の違いが、付楠と健太の両方の視点から洗い出されているあたりが、興味深い。そして、それを乗り越えて深い愛で結ばれる恵恵と健太の関係が、やはり奇跡といっていいような出会いであったと思わされる反面、若く柔軟な人たちは、そういう違いをいとも簡単に乗り越えることができるのだということも気づかされる。
◆付楠の手記の部分で衝撃的なのは、恵恵が入院していた日中友好病院で出会う他の乳がん患者の聞くも悲惨ないくつかのエピソードである。
◆例えば、こんな話。ある中年女性は娘を生んだあと乳がんになる。すると舅がすぐに彼女に離婚するように要求した。「もし要求に従うならがんの治療費として100万元出してやる。だが、離婚に応じないなら一銭たりとも出さない」と。当然彼女は離婚するしかなかった。
◆ある女性は夫と共同で会社を興し、ともに苦労して財産を築いた。だが彼女が乳がんとわかったとき、夫は若い愛人をつくり、しかもその若い愛人を家に連れてきた。そんな状態になっても彼女は離婚できない。夫が離婚に応じないのだ。離婚すれば共同財産の半分は彼女に渡さなければならない。だが、夫は彼女のがんがすでに肝臓に転移して死期が間近なのを知っている。彼女が死ねば財産は全部自分のものだ。愛人との関係を病に苦しむ妻に見せつけながら、その死を待ち望んでいるのだ。彼女にはすでに裁判沙汰を興す気力も失せて、ただ残される二人の娘のために強い副作用のある化学療法を続けている。が、付楠がある日、その女性の携帯電話に電話をかけてみると、その番号は不通になっていた。たぶんすでに亡くなっている。
◆中国では、高額のがん治療のために財産を使い果たし、人間関係も失われ、貧しく孤独の中でなすすべもなく死んでゆく人たちの方が圧倒的多数であることが、これらエピソードでうかがえる。
◆だから、多くの中国人、特に女性が、恵恵と彼女を献身的に看護する夫・健太の関係性を「うらやましい」と思う。院内では恵恵と健太は「患者たちの希望」だと言われ、理想のカップルとして憧れられ、看護婦や医師、外来患者の間まで、こんな夫の献身を見たことがないと、噂になるほどだったという。
◆教養はあるが決して大金持ちでもない、ごく普通の中国人である付楠は、病院で他の乳がん女性の悲惨な境遇を多く目の当たりにしたからこそ、健太の献身が奇跡的なのだと、感動し、深く感謝した。実際、恵恵が乳がんだとわかったととき、健太は迷いなくそれまで務めていた高校教師を辞職し北京に飛んで、結婚した。化学治療を受ける前に、副作用で髪をなくす彼女を励ますつもりで丸坊主になって見せた。がんの痛みを訴える恵恵を一晩中マッサージしていた。そういう惜しみない、見返りをもとめない愛は、やはり中国人男性にはあまり見られないのだ。
◆農村にいけば、まだまだ男尊女卑の価値観は強く、男の子を生めないというだけで、婚家から追い出される嫁の話とかふつうにころがっている。農村に限らず、今の中国ではまだ、女の価値基準は、若くて健康で子供が産めることだ。乳がんという、たとえ一命を取り留めても、出産も難しく、乳房という女性的なフォルムを失った女性が、特に夫や婚家から受ける仕打ちは、たいへん冷酷だ。
◆それは中国が相対的に貧しいからというのもあるだろうが、嫁という存在が、一族にとって血の繋がっていない部外者であり、結婚が、男女2人の恋愛の結果として生じるというよりは、子供を生み増やすためや家と家、一族と一族を血縁で結ぶという、意味合いがまだ強いということもある。女性が一個の人間として評価されるのではなく、産む道具、ファミリーの繁栄のための駒として扱われる伝統・価値観がまだある。すべての中国女性に当てはまるわけではないが、そういう傾向はある。このあたりは、東洋史家の宮脇淳子さんとの対談本「中国美女の正体」(フォレスト出版)でも解説してある。
◆だから付楠は、健太の惜しみない愛、献身の理由を、健太が日本人であるということとつなげている。「我在天国…」を読めば、それは感じることができる。恵恵は日本での留学生活を生き生きと母親に伝えており、学校やバイト先での経験や人間関係を通じて学んだ日本人的な価値観や習慣を非常に好ましいものとして語っていた。付楠が恵恵の卒業式のために日本に初めて訪れたときに、日本人的な心遣いや思いやりに対する印象も手記に細かく書いているのだが、それは普通の日本を知らない中国人が初めて見る日本人像の一つの典型であると思う。
◆たとえば、レストランのバイトである恵恵と常連客たちとの関係。卒業に合わせて恵恵がバイトを辞めるときに、常連客がわざわざプレゼントをもってお別れを言いにくる様子を付楠はものすごく感動的なことのように書いている。店の看板娘と常連客のこうした下心なしの交流は、日本ではわりと普通だと思うが、考えてみれば、中国では店員と客の間の上下関係は、確かにもっとはっきりとあからさまなもので、対等の交流というのは、あんまり見かけなかったかもしれない。もちろん、日本でも最近は、他人への心遣いや思いやりというものがずいぶん色褪せてきたのだが。
◆おそらく付楠が手記を書いた動機の中に、健太のすばらしさを周囲の人に知ってもらいたい、この日本人男性が娘に捧げた愛と献身を知ってもらいたい(娘がその献身を受けるだけの素晴らしい女性だったということともに)という気持ちがあったのだと思う。そして言外に、この中国の男たちの女性たちに対する情けの薄さを比較しているかもしれない。この物語が進行しているのは2003年から2011年にかけての時代。日中関係が一番荒波にもまれている時代である。日本人を知らない中国人の少なからずが、日本人は野蛮人で、とんでもない人たちだと批判的、否定的な見方をしていた。少なくとも、建前上の言葉では日本人を批判するのが当然とされた時代だった。付楠にすれば、本当の日本人を知らないくせに、日本人を批判しているのだと歯がゆく思ったことだろう。
◆この本にさほど政治色はないのだが、やはり行間に、恵恵の青春であった日本留学時代と、生涯の伴侶と出会わせてくれた日本へ思い、感謝に近い感情が感じられる。実際にこの本の中国語版原作を読んで「日本人の印象が変わった」という感想も多く寄せられたという。
◆一方、原作にはない健太の手記は、日本人の視点で、中国特有の濃密なファミリーを浮き彫りにしている。恵恵のために、両親だけでなく叔父叔母従妹らが、一丸となって支えあう。恵恵は一人っ子政策時代の一人っ子だが、その母親らの兄弟姉妹親族の結束の強さは、核家族世代の一人っ子の健太には実に新鮮で、素晴らしいものに感じられたようだ。中国も実際のところ、この中国的家族の絆は全体として薄れつつあるのだが、恵恵の家庭は、典型的な結束の強い中国的ファミリーの家だった。ちなみに、その恵恵のファミリーの中に、日本でも人気のある紀行作家の毛丹青氏がいる。
◆健太が、かくも恵恵に惹かれた理由の一つに、この濃密な中国的ファミリー、家族の絆に強い憧れを抱いたからだということがうかがえる。たいていの若者はそういった濃すぎる家族の情愛、しがらみをうっとおしく思うものだが、健太は違った。祖父母の面倒までを自分の責任しとして考える恵恵の生き方、価値観に感動し、自ら望んで、この中国的ファミリーの中に身一つで飛び込み、実の息子のように迎え入れられる。
◆ちなみに恵恵は結婚前に、健太の老人ホームに入っている祖母まで自分で引き取って面倒を見たいと言って、健太を感動させるシーンがある。いつか北京郊外に大きいおうちをかって、健太の家族と恵恵の家族、一緒に暮らしましょう、と。恵恵は健太と一緒に、家族まるごと背負う覚悟を最初から普通にもっていた。自分のことだけを考えればいい(あるいは成人しても親のすねをできるだけかじりたい人も多い)と考えるのが日本の若者の標準として見てきた健太は、恵恵の気概に圧倒されるのだった。
◆そういえば、日本人女性が中国人男性に嫁ぎ、田舎の家族主義のなかで奮闘する苦労と献身の物語は個人的にいくつか知っているケースがあるが、健太のように日本人男性で、そのファミリーの中にどっぷりつかってしまう話はやはり珍しい、と思う。中国人嫁が日本に嫁ぎ、日本式の家族になじんで、日本人嫁以上に姑に尽くす話も個人レベルで知っているが、中国人の一人息子が、自分の親を中国に置いたまま日本人女性と結婚して、嫁の実家に入り込み、日本の大家族の一員として献身する例は、ふつう考えられない。いまどきの若い日本人男性の「家」に対するこだわりのなさなんかも、本書を読んで気づかされた点だ。
◆単にボーイミーツガールの純愛物語というだけでも、感動的な闘病記というだけでもなく、中国の残酷な医療現場や、日中の人間関係、家族観の違いなど、いろんな背景が読み取れることが、読み物としての深みになっていると思う。優等生的なメッセージを読み取るとしたら、中国人の付楠が、日本人の血のつながらない他人(妻も含む)への情の深さを奇跡のように尊く感じ、日本人の健太が血で結ばれたファミリーの圧倒的な結束に憧れるように、お互いがお互いにないものを見出し、それを自分に獲得しようとする気持ちが、文化や価値観の壁を越えた新たな人の結びつきを生む、ということだ。普遍的な人間関係の基本ではあるが、今の私たちには忘れがちなことかもしれない。
◆最後に、付け加えておくと、この恵恵の夫、岡崎健太さんと2008年初夏にお会いしている。本書でも出てくるSOHOのカレー店で、毛丹青氏と翻訳家の泉京鹿と一緒にお会いした。記念撮影の写真が残っている。時期的に恵恵さんが小康状態のとき、彼女と二人三脚でカレー店を運営していこうと希望を見出していた。健太さんは笑顔だった。このころ、恵恵のことは聞いていたけれど、すっかり治って元気なんだと思っていた。
◆健太さんが笑顔の後ろに背負っているものに、私自身まったく気づかずにいたことへの、少しのうしろめたさが、こんな長い書評を書いてしまった理由の一つだと思う。最後まで読んでくれてありがとう。
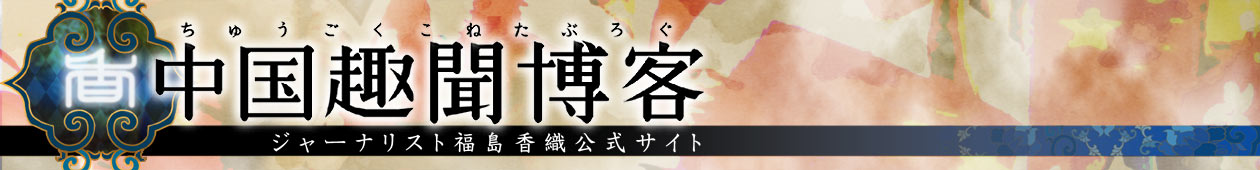


やっぱり福島さんの文章はある程度長い方が読ませますね。いや一気に読んでしまいました。恵恵さんが幸せな人生だったと思ってくれてたらいいな。本も探して読んでみます。
長いのに、最後まで読んでくれてありがとう。本、泣けますよ。
遅ればせながら公式サイト開設おめでとうございます。
わたしもこの手の話に弱いので、書評を見ただけで目頭が熱くなってきました。
で、話は変わりますが、タグへのリンク(もしくはタグの設定)にバグがあるようです。
あと、ツイッターで紹介しようとしたのですが、記事のタイトルは自動的に反映されないのですね。普通記事のタイトルは自動的に反映されるものなのですが。意図的にそのように設定しているのでしょうか。
物語の例から中国に健太みたいな献身的な男性がいないと断定することが誠にあまりにも無知で偏見そのものです。客観的に物事を論じることができなければ、中国屋としては価値が下がりますよ。