■30年以上の投獄生活と数々の拷問にも絶望することなくほほえみ続けることができる精神の強靱さ。不屈のチベット僧・パルデン・ギャツォの生きように魂を揺さぶられたひとり、NY在住の日本人女性ドキュメンタリー監督、楽真琴(ささ・まこと)さん(写真↓福島撮影)は、パルデンのドキュメンタリーを撮るべく、その活動、暮らしを追いはじめる。

■楽真琴「2006年2月のトリノ(イタリア)五輪で、パルデンが、チベットの自由を訴えるハンガーストライキを行うことをインターネットの情報で知って、すぐ飛んでいきました。本当は最初、(ハンガーストライキ活動の)主催者に怒ったんですよ。70過ぎの老齢でハンガーストライキなんてあまりにも無茶だ、そんなことさせるな、と」
■とりあえず現場にいき、ハンガーストライキのキャンプに2日泊まり込み撮影を開始する。
■楽真琴「夜中、真っ暗なテントの中で寝ているとパルデンの寝息がする。ああ、この寝息がいつとまるか分からないと思うと、もうたまらなくて。あまり密着しすぎると客観性が保てないとおもって、2日後にはサポーターの家に泊まらせてもらうことにしました。パルデンは死を覚悟していて、チベット・サポーターからの本などの差し入れにも、『私は死ににきたからこれは持って帰れない』と断っていました。それをみて、涙が止まらなくて。30年以上ずっと投獄されて、やっと自由になっても、こんな風に闘いつづける。こんなに胸に迫ってくることはないのに、なぜテレビや新聞は取材してくれないんだろう、IOCは理解してくれないんだろうって怒りがわいてきた」
(ハンガーストライキのときの記者会見、アップリンク提供)

■あまりに感情移入しすぎかと思われたが、それが予想以上の緊迫した映像となった。パルデンの30年あまりの時間は、釈放されて自由になったからといって取り戻せるような甘いものではなかった。彼が生きながらえた背景には数え切れない同胞の死がある。彼が生きるということは、その無数の無念の死を背負いつづけることでもあった。
■ドキュメンタリー映画の中でパルデンは語る。--監獄の中で、飢えと渇きに苦しむ同房の仲間が水をください、とパルデンに訴える。何も持たぬパルデンは、口の中で唾を絞り出し、それを苦しむ仲間に口移しに与えた。仲間はその聖なる水を飲み下しありがとうと繰り返すが、やがて死ぬ。その死のまぎわ、パルデンに、外に出たら、この惨状をみなに知らせる仕事をしてほしいと言いのこす。
■楽真琴「私は映画の中であえて、チベット独立、という思想をメッセージとして込めました。インディペンデンス(独立)かオートノミー(自治)か、最初、外国人としてそんなこと言えるわけないと思っていました。私は部外者で、それはチベット人が最後に決めることで、私は遠慮があったんですよね」
■楽真琴「でも、チベットで触れた名前の言えない人たち、その人たちにふれて、より独立というものが言える人が言っていかなきゃだめだな状況にあるんだなと思って」「なぜなら、チベットは独立国家だったし、私のまわりのチベット人もみんな独立がほしいと思っている。(独立をあきらめ自治を求める)ダライ・ラマにはダライ・ラマの立場があるけど、外国人の立場で独立を言い続けることはすごく重要なことだから。だからドキュメンタリーのなかに独立っていうことを入れたかった。ただの仏教ドキュメンタリーにしたくはなかったんです」
■ダライ・ラマ14世のインタビューは6回断られた。それでもしつこくオファーし続ける。「また、日本人のあの子、きているよ」とダラムサラで噂になった。最後に、インタビュー申請が承諾されたき、奇跡を感じた。
■編集に一年かけて、2008年、ドキュメンタリー映画は完成した。楽さんがこの映画をパルデンに最初に見せたのはその年のトライベッカ・フィルムフェスティバルのプレミアム上映会で。場内の明かりがおとされてから、こっそりと会場に入ってきてこの映画をみたパルデンは涙を流し続けていたという。
■楽真琴「映画を撮っている間、いつも責任を感じていた。彼のストーリー、ライフ、ジャスティス(正義)を撮らなきゃ、と。多くの人の命がかかっているのだと言い聞かせてきました。今でも責任が果たせたかどうか分からないんですけど、少なくとも、彼の目に涙を浮かべさせるだけのものはできたと…」
■楽さんは人の安全がかかわるために、ここには書けない制作の秘話も話てくれた。観光客としてチベット自治区に入りカメラを回す中で、チベット族の心の奥にある、決して表に見せることのできない傷あとから今も血が流れていることを知る。1時間あまりのインタビュー中、楽さん自身が、まるでその痛みが自分のものであるかのように、涙をぽろぽろこぼしていた。
■この映画はチベット独立、フリーチベットを強く打ち出しているわりには、政治臭はあまり感じない。ただ、重い使命を背負って苛酷な人生に打ち勝ってきた人の神々しいまでの強さが印象にのこる。それを撮っているのが、泣き虫で感情過多で、まだ女の子の面影のある女性監督というのが驚きであると同時に、なぜか納得もできてしまう。
■この映画が発表されて以降、楽さんも多少の嫌がらせをうけているという。「サンフランシスコのフィルムフェスティバルでの上映会に対して中国大使館から『雪の下の炎』を上映リストからおとすようにを抗議を受けたこともありました。もちろん、その抗議は無視されましたけれど。あと、テンジンさんとか、ダライさんとかいう名前のウイルス入りファイル添付つきメールがきたり…」
■日本では4月から全国各地で上映会がはじまるという。それにあわせて、パルデン師を日本に招こうという動きもあるようだ。実現すれば嬉しいね。チベット問題に興味のある人もない人も、チベット独立を支持する人も反対の人も、永遠に続くかのような万年雪の下でも燃え続ける炎がこの世にあるのだと、知ってほしい。いかなる恐ろしい暴力であっても、目もくらむような富・経済力であっても、完璧にみえる情報操作・統制でも屈服させることのできぬ魂というものが存在する。その事実を知るだけで、世界が少しだけよい方向に変わる気がしないだろうか。
■「不正には屈しないという私たちの意志は、たとえていうなら、決して消せない炎だ。思い返してみるに、自由への思いは雪の下でくすぶり続ける炎のようなものだった」
パルデン・ギャツォはかく語りき。

(アップリンク提供)
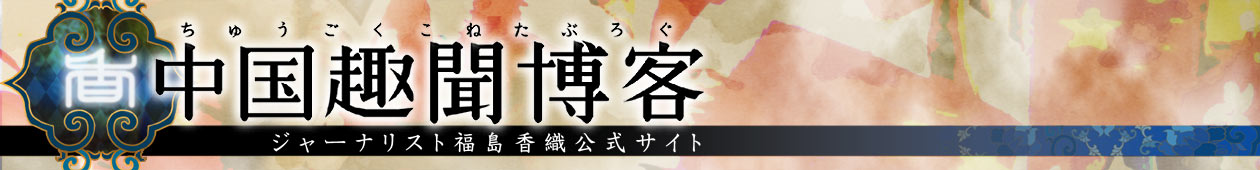

To Cosplayさん
>アネキ、マジ怒った?スイマセン。分かったよ。お休みなさい。
暫くROMっていたが、いい加減に頭にきた。
己の身も養えないような阿Qのくせに、相手が女だからと甘く見てくだらない書込ばかりして荒らしをしやがって。
お前のような馬鹿は生きている価値が無い。道頓堀でカーネルおじさんのの銅像と心中しろ。
チベットに自由を。
福島記者
> この映画が発表されて以降、楽さんも多少の嫌がらせをうけているという。
自らを”中華”と称する割にはケツの穴が小さいというか…どこへ行ってもそういう努力だけは忘れないのですね…♪
> …その事実を知るだけで、世界が少しだけよい方向に変わる気がしないだろうか。
少なくともそう信じたいと考えます。 「解放」と云う名の「弾圧」を体感した経験のない私でも、何かを考えられる筈ですから…
上映、楽しみにしています。
楽真琴さんの読み仮名がわからない方が多いとおもわれるので、読み仮名をふりました。配慮がたらなくてすみません。楽(ささ)とか楽々(ささ)とか、苗字に使うときはこう読みます。小鳥遊(たかなし)、上高垣内(うえたかがいと)、甕(もたい)。外国の人にはとうてい読めない苗字には振り仮名をつけるべきでした。ちなみに上記の苗字は、全部私の同窓や知り合いにいます。奈良って珍しい苗字の人があつまるところなのか?また、ご推察のように楽真琴は芸名であります。おばあ様が考えてくださったそうです。
福島様
コメント欄で失礼します。
>自らを”中華”と称する割には○○の穴が小さいというか…
>どこへ行ってもそういう努力だけは忘れないのですね…♪
○○の穴が大きいといえば日本人でしょうか?
>チベットに自由を。
僕は安定が先だと思いますが・・・
どっちかといえば、もっと中国政府と戦え!!血を流せ!!
のようにみえます。
By 在日7年目の中国人より
To Cosplayさん
>そんなマスコミは、解散しましょうね。
自己矛盾を自覚した「負い目」を感じているうちは、世間というよくわからない自己規定された「亡者」によってありもしない集団的圧力でこの世から精神的に追放され、自ら「自死」(あるいは「隠遁」「退却」「自己逃避」等等の擬似的行為)気配の中にいるでしょうね。
マスコミが権力構造の中に組み込まれているというのは言わずもがな。記者もご他聞に漏れず。
「きれいごと言って」謝罪などされるより「言い逃れの術」を身に着けてうまく交わすほうが、「現代的」売文業としては精神衛生上ふさわしいし、論戦の永続の期待により社会の恒常性は逆に担保される、ということをこのいい加減な社会は望んでいませんでしょうか。
「我こそは告発者なり」と「ロンギヌスの槍」でも取らぬ限りは。
しかし、世界は支配できても己の神を殺すという二律背反は、いかんともしがたい苦悩でしょうけれども。
「発言」は「消せない」。
言説には、「本人の名前」が識別記号として「符牒」されたまま、永遠に「売買」あるいは「無償譲渡」される。一切は「焚書」では消し去れなかったのは西欧の歴史を見ればわかること。
本人の意図とは違うように「失言」「自己矛盾」などと一切が悪評とともに受け止められるのがこの世の常だとするならばという前提の下では。
それでも誤解を解くために釈明の機会を求めるというエドワード・サイードのごとき人もいるけれど、傷口をふさぐのは「釈明」「弁解」「自己主張」ばかりではないというマス化した社会という現実を前にした相克はいかに埋めるべきか。
こういう集団の中の個々の「決断」こそ「自己責任」として語られるべき問題。